ドイツ・ウーラント紀行①

◆「愛の夢」第2番
幸せな死
私は死んだ
愛の至福の前で
私は埋葬された
あのひとの腕のなかで
私は目覚めた
あのひとの口づけから
私は天国を見た
あのひとの瞳のなかに
Gestorben war ich
Vor Liebeswonne:
Begraben lag ich
In ihren Armen;
Erwecket ward ich
Von ihren Küssen;
Den Himmel sah ich
In ihren Augen.
あの人の腕に抱かれるのなら、死んでもいい。青年なら誰しもが思う恋心を歌った「幸せな死」(Seliger Tod)をつくったのはドイツの詩人、ルートヴィッヒ・ウーラント(1787~1869)です。ちょっと気恥ずかしくなるような詩ですが、1807年、彼が二十歳のころの作品と聞けば、わが青春の想いもかくなりき、と言いたくなります。(下の写真はウーラントの肖像画)

この詩に魅かれた人は多かったようで、1849年に「私は死んだ」(Gestorben war ich)という題名の歌曲となり、その翌年には、別の歌曲と組み合わせたピアノの独奏曲に編曲されました。「三つの夜想曲」との副題を持つ「愛の夢」で、作曲者はハンガリーのフランツ・リスト(1811~1886)です。
「私は死んだ」は「愛の夢」の第2番で、第1番の「高貴な愛」(Liebesträume)とともに原詩はウーラントです。狂おしい思いが伝わってくる素敵な歌曲だと思いますが、「愛の夢」で誰もが思い浮かべるのは残念ながら第3番で、原詩はフェルディナント・フライリヒラートの「おお、愛しうる限り愛せ」(O lieb so lang du lieben kannst)です。第3番は、ピアノ曲として有名になったことで、歌曲としても演奏されることも多いようですが、ほかの2曲はあまり歌われることはなく、残念ながらウーラントの詩であることもあまり知られていません。
ウーラントの詩集はドイツでは出版されているのですが、日本では単独の詩集としては出版されていません。ドイツは歌曲が盛んで、ウーラントの詩もカール・レーヴェ(1796~1869)、フランツ・シューベルト(1797~1828)、フェリックス・メンデルスゾーン(1809~1847)、ヨハネス・ブラームス(1833~1897)などが歌曲にしています。有名なのはシューベルトの「春の想い」(Frühlingsglaube)ですが、ほかはあまり歌われていないようです。(下の写真はドイツで刊行されているウーラントの詩集)
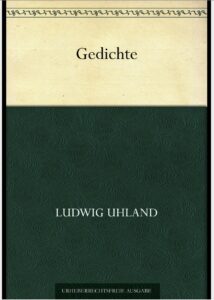
ということで、ウーラントという詩人は、マイナーな存在なのですが、その詩人の作品のなかでも、マイナーと思われる「渡しにて」(Auf der Überfahrt、以下「渡し」)という詩をめぐって、ドイツまで旅をした話を書こうと思います。「渡し』をめぐる「ドイツ・ウーラント紀行」です。紀行に入る前に、「渡し」という詩を紹介しておきます。
◆「渡し」という詩
渡し場
年(とし)流れけり この川を
ひとたび越えし その日より
入り日に映(は)ゆる 岸の城
堰(せき)に乱るる 水の声
同じ小舟(おぶね)の 旅人は
二人の友と われなりき
一人はおもわ 父に似て
若きは希望(のぞみ)に 燃えたりき
一人は静けく 世にありて
静けきさまに 世をさりつ
若きは嵐の なかに生き
嵐のなかに 身を果てぬ
倖(さち)多かりし そのかみを
しのべば死の手に うばわれし
いとしき友の 亡きあとの
さびしさ胸に せまるかな
さあれ友垣(ともがき) 結(ゆ)うすべは
霊(たま)と霊との 語(かた)らいぞ
かの日の霊の 語らいに
結(むす)びしきづな 解(と)けめやも
受けよ舟人(ふなびと) 舟代(ふなしろ)を
受けよ三人(みたり)の 舟代を
二人の霊(たま)と うち連(つ)れて
ふたたび越えぬ この川を
Auf der Überfahrt
Über diesen Strom, vor Jahren,
Bin ich einmal schon gefahren.
Hier die Burg im Abendschimmer,
Drüben rauscht das Wehr wie immer.
Und von diesem Kahn umschlossen
Waren mit mir zween Genossen:
Ach ! ein Freund, ein vatergleicher,
Und ein junger, hoffnungsreicher.
Jener wirkte still hienieden,
Und so ist er auch geschieden.
Dieser, brausend vor uns allen,
Ist in Kampf und Sturm gefallen.
So, wenn ich vergangner Tage,
Glücklicher, zu denken wage,
Muss ich stets Genossen missen,
Teure, die der Tod entrissen.
Doch, was alle Freundschaft bindet,
Ist, wenn Geist zu Geist sich findet;
Geistig waren jene Stunden,
Geistern bin ich noch verbunden.---
Nimm nur, Fährmann, nimm die Miete,
Die ich gerne dreifach biete !
Zween, die mit mir überfuhren,
Waren geistige Naturen.
これがドイツ紀行の目的であるウーラントの詩です。格調の高い文語訳は、猪間驥一(1896~1969)と小出健(1928~2021)の共訳です。1956年、中央大学の教授だった猪間が朝日新聞の「声」欄に、幼いころに読んだ記憶のある詩の作者を知りたいという投書をしました。それがきっかけで、ウーラントの詩とわかり、投書に回答した小出との共訳という形で、この投書をめぐる話題を記事にした「週刊朝日」に掲載されたものです。
冒頭の「幸せな死」は、格調とは無縁の拙訳です。ドイツ語は全くわからないのですが、英語とは同じゲルマン語派だというのを頼りにドイツ語の原詩をgoogleの翻訳ソフトで英訳し、それをもとに日本語にしました。「たぶんこんな感じじゃないか劇場」です。すみません。
亡くなった友と渡った渡し舟に乗って友を偲ぶ。ひとりの友は静かな暮らしのなかに亡くなったが、もうひとりは戦場の嵐の中で命を落とした。舟を降りるときに友の分も含めた3人分の船賃を船頭に渡す。ぐっとくる詩ですね。1823年の作品ですから、ウーラントが36歳のころです。恋人に抱かれて死にたいという青年の情熱は感じませんが、3人分の船賃を払うというのは男のロマンかもしれません。
◆ドイツ旅行に駆り立てたもの
ドイツ旅行をしたのは、松田昌幸さんと長女の美木子さん、中村喜一さん、釜澤克彦さん、それに私と妻の惠の6人です。男4人は、「ウーラント同“窓”会」というサークルの有志で、いずれも後期高齢者です。「海外旅行はこれが最後だろうな」などと言いながら、ドイツ旅行を敢行したのは、このサークルが2022年1月に出版した『「渡し」にはドラマがあった』(荒蝦夷)という本(下の写真)と、サークルの発起人でもある松田さんの投書(下の写真)が2022年2月16日の朝日新聞「声」欄に掲載されたことがきっかけです。
「ウーラント同“窓”会」は、「渡し」をめぐるドラマの一端を私が新聞のコラムに書いたのが縁で、「渡し」に興味を持つ人たちが集まってできたサークルで、私もそこに加わりました。『「渡し」にはドラマがあった』は、ドイツの詩である「渡し」が日本でどのように受容されてきたのか、という長いドラマを会員それぞれが書いたもので、本が出版された折に、私は「情報屋台」でその概要を紹介しています。
この渡しがどこなのか、この詩に感銘した中央大学教授だった猪間驥一(1896~1969)は1961年にドイツに留学した折に、ハイデルベルクを訪ね、この詩が歌曲になっていないかを調べます。そんないきさつもあって、ライン川の支流であるネッカー川のほとりにあるハイデルベルクが渡しの舞台と思われていました。松田さんが2008年にこの詩の足跡を訪ねてドイツを旅したときにも、真っ先に向かったのはハイデルベルクでした。この町を見下ろす「哲学の小道」から夕陽に照らされたハイデルベルク城とネッカー川を見たときに、「渡し」の「入り日に映ゆる岸の城 堰に乱るる水の声」の一節が思い浮かんだと言います。
しかし、詩の舞台はハイデルベルクではなく、シュトゥッツガルト郊外のホーフェンではないかと、釜澤さんが言い出しました。「渡し」の舞台であるという案内板が2017年に設置されたことを釜澤さんがネット上で「発見」したからです。そこで、ウーラント同“窓”会のなかからは、あらためて詩の舞台であるホーフェンのネッカー川を見たいという声が出てきました。
松田さんが投稿した「声」は次の通りで、この投書で、さらにホーフェンへの思いが強まったというわけです。
66年前の一通の投書が縁 本出版 無職 松田昌幸 (東京都 85)
1956年9月の声欄に掲載された「老来五十年 まぶたの詩」という投書がきっかけとなり、「『渡し』にはドラマがあった」という本が最近、出版された。投書は、次のような詩の出典を尋ねる内容だった。
――ひとりの老人がある川の渡し船に乗り、船頭に多めの渡し賃を払う。驚く船頭に老人は言う。「それだけ取っておいてください。お前さんには1人としか見えなかっただろうが、私は連れと一緒だったつもりだから」。老人は若かりし頃、亡き友人らと渡し船に乗ったことがあったのだ――。
当時、すぐさま反響があり、ドイツの詩人ルートヴィッヒ・ウーラントの19世紀の作品「渡し場」で、日本に紹介したのは新渡戸稲造。歌曲になっていたこともわかった。その後も関連投書がいくつか掲載され、それが縁で、「ウーラント同“窓”会」もできた。その交流の成果としてまとまったのが今回の本。平均年齢80歳超のメンバーの一人として、声欄に感謝したい。

ドイツ旅行の行程については、商社員でドイツ駐在の経験もある釜澤さんが詳細なプランを立ててくれました。東京からフランクフルトに行き、そこから鉄道でハイデルベルク、シュトゥットガルト、テュービンゲン、ミュンヘンを回り、フランクフルトから帰国するという旅です。5月22日の深夜便で出発し、31日の午前に戻るという10日間の旅(ドイツ国内での宿泊は7泊)という旅でした。旅の様子は次回以降にしますが、ロシアによるウクライナ侵攻のおかげで、日本から欧州が遠くなったことを記しておきます。
◆ウクライナ戦争の余波
欧州は米国東海岸よりも近いと思っていたのですが、フランクフルトまでの時間がほぼ15時間と知って驚きました。ウクライナ戦争のおかげでロシア上空を飛行できないことになり、ANAのフランクフルト便は、アラスカ経由の「北回り」でスカンジナビア半島からドイツに入ることになったためです。ロシア経由に比べて3時間も長くかかることになったのです。帰りのルフトハンザ便は中央アジア経由の「南回り」で、こちらは12時間半の飛行時間でした。
フランクフルトとの往復で地球を一回りした感じですが、思わぬところで戦争の影響を受けたわけで、往復の飛行機の中では、心の中でプーチンをののしり続けていました。
私の勉強会仲間であるINPEXソリューションズ上席研究員の篠原建仁さんによると、ウクライナ戦争以来、ユーラシア大陸の東西を結ぶ陸上及び海上の交易路として「カスピ海ルート」が重要視されるようになっているそうです。日本にとっても欧州と結ぶロシアを経由しないルートとして着目されるようになったのです。復路のフランクフルト・羽田便は、まさにこのルートに沿って、カスピ海の上空から中央アジア、モンゴルを超えて日本列島に入ったので、シルクロードの復活ともいえる「カスピ海ルート」の重要性を上空から実感したわけです。
(冒頭の写真は、ハイデルベルクの「哲学の道」から望むハイデルベルク城と市街地=2023年5月23日、筆者写す)
未分類の関連記事
| 前の記事へ | 次の記事へ |




コメントする