ドイツ・ウーラント紀行⑦完

サッカーチーム、バイエルンの優勝に沸く喧噪のミュンヘンからフランクフルトに列車で4時間かけて移動、いよいよドイツ旅行は終盤です。翌朝、最後の観光となるケルン大聖堂を往復するツアーに参加しました。
往路は、ライン川に沿った道を進んだので、河畔のワイン畑とワイナリーをのぞいたり、「つぐみ横丁」が有名なリューデスハイムの町を歩いたり、右岸から左岸にフェリーで渡ったり、古い町並みが残るバッハラッハを歩いたり、ラインの風景を楽しみました。船着き場ごとに古城と町があるのをだとりながら、この川の周辺が古くから水運で栄えてきたのだと実感しました。(下の写真は、ヴィンケル近くのワイン畑とワイナリー、リューデスハイムのつぐみ横丁、ライン川を渡るフェリー甲板の筆者、バッハラッハの古い街並み)




サンクト・ゴアールの手前では、対岸のローレライの岩山を見ながら、私たちは同じ歌を口ずさみました。もしろん、ハインリヒ・ハイネ(1797~1856)作詞、近藤朔風訳詩の「ローレライ」(作曲はフリードリヒ・ジルヒヤー)です。(下の写真はローレライの岩山)

なじかは知らねど 心わびて
昔の伝説(つたえ)は そぞろ身にしむ
ハイネの原詩の訳文と比べると、近藤朔風の訳詞のほうが、そぞろ身に沁むように思えます。それはさておき、ハイネのローレライは、恋に破れてライン川に身を投げた乙女が水の精となって漁師を誘惑するというローレライ伝説をもとにしたものです。この詩は1824年に作られ、1827年に刊行されたハイネの『歌の本』(Buch der Lieder)に収められました。岩山に座る美しい娘が口ずさむ旋律の魔力に惹きつけられ、船人は迫る岩礁に気付かず波にのまれる、というハイネの詩は、とてもロマンティックなものに思えます。(下の写真はハインリヒ・ハイネの肖像画)

そうだとすると、ローレライから12年後の1836年に出版された『ロマン派』(邦題は『ドイツ・ロマン派』)で、厳しくロマン派の文学者たちを批判したのは、なぜだったのでしょうか。ウーラントの詩についても、もはや心に響かないと、突き放しています。
ハイネはこの本のなかで、ウーラントがほとんど詩を書かなくなったのは、彼の詩的な好みが政治的な立場との矛盾するようになったからだとして、次のように評しています。(一部、割愛)。
「カトリック的封建的過去を、あのように美しいバラードやロマンツェで歌うことのできた哀歌詩人は、ヴュッテンベルクの身分制議会で、国民の権利の熱心な代表者となり、市民の平等と思想の自由の大胆な弁士となった。この民主主義的なプロテスタント的な意向が、彼にあっては本物であり、純粋であることを、ウーラント氏は、この意向のために払った大きな個人的犠牲によって証明した。新しい時代のことをそのように誠実に考えるが故にこそ、古い時代の古い歌を、もはや以前の感激をもって歌い続けることはできなかった」(山崎章甫訳『ドイツ・ロマン派』)
ドイツ・ロマン派の詩人たちは、ロマンのお花畑に隠れて、ドイツの現実を見ようとしない、という視点で、ドイツ・ロマン派批判を展開したハイネからすると、詩人ではなく、政治家として自主主義の熱弁をふるったほうのウーラントこそ本物だと言いたいのでしょう。
たしかに、ウーラントが身分制議会の議員になった1819年ごろのドイツは、政治変革のうねりが強くなった時期で、ウーラントは、民主派の議員として、市民の権利を擁護、拡大するのに精いっぱいで、ロマンあふれる詩作にふける余裕はなかったのかもしれません。議員在職中の1823年に作った「渡し」は、例外的な詩作であり、詩人ではなく友を慕うひとりの人間としての思いが込められた作品とみるべきかもしれません。
ただ、ハイネさんに反論するほどの知識も見識もありませんが、ウーラントがロマン派として詩作に励んだころは、自由・平等・友愛を掲げたフランス革命(1789)を経て、ナポレオンが共和政治を敷きながら封建制の残る欧州に領土や勢力圏を広げていた時代でもあります。民主主義の光をフランスに見ることはできましたが、ドイツ諸邦はまだ封建制の闇の中でした。
ドイツ・ロマン派の詩人たちが自由な精神をギリシャ神話の世界に見出し、かれらの幻想領域を中世に広げていった背景には、フランスのような革命はまだしも、せめて精神の自由を謳歌したいという願望があったように思います。とすれば、ロマンのお花畑は、現実から逃げ込む場所ではなく、現実を変革するための揺籃の場所でもあったように思えます。
ウーラントが1862年に亡くなって12年後、エマ夫人は『ルートヴィヒ・ウーラントの生涯』(以下、『伝記』)を出版します。そのなかで、エマ夫人は、ウーラントは中世を愛していたが、復古主義者ではないとして、ウーラントがケルン大聖堂の拡張に熱心ではなかったと、証言しています。ウーラントは次のようなことを語っていたと、エマ夫人は書いています。(下の写真はエマ・ウーラントの『ルートヴィヒ・ウーラントの生涯』)
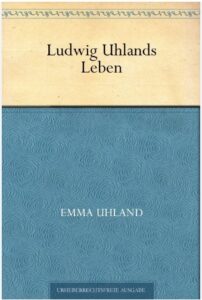
「大聖堂の建設が着工された当時は、マスターと職人がいて、石彫刻や絵画の流派は創造力をそこに染み込ませ、そうしたアイデアの中で生きていた。それを私たちの時代に持ち込むことは、もはやできない。それは強制された熱意だ」
大聖堂は、それ以前の聖堂が1248年に焼失したすぐあとから建設がはじまり、1322年には内陣が完成しますが、財政難などから塔の建設は先送りされます。巨大なふたつの塔の建設は、500年超の歳月を経た1842年からで、プロイセン政府の財政援助のもとで進められます。高さ157メートルの二つの塔が並ぶ世界最大のゴシック様式の建築物が完成したのは1880年です。
ウーラントが熱意を見せなかったという拡張工事は、この拡張工事のことでしょう。ウーラントは、13世紀から14世紀にかけて、聖堂の建設に携わった人々の思いを無視して、国家の威容を見せるために行われた拡張工事には、賛同できなかったのでしょう。
◆ケルン大聖堂
ローレライの岩山からハイネのロマン派論の支流に入ってしまいましたが、私たちのツアーは、ライン川沿いの道をさらに進み、目的地であるケルン大聖堂に到着しました。ウーラントの思いとは裏腹に、19世紀の拡張工事で完成した巨大建築に、私たちは圧倒されました。内陣の完成は14世紀、外陣の完成は19世紀というつぎはぎ建築ですが、拡張からも143年経つ大聖堂は、第2次大戦で爆撃を受けた影響もあるのでしょう、十分に古く黒ずんでいて、つぎはぎとは思えない威厳さを持った壮大な姿を見せていました。(下の写真は、ケルン大聖堂の内部)

大聖堂のところどころでは、工事用のテントが張られたり、足場が組まれたり、している場所がありました。これだけの大きな建物になると、維持管理も大変だと思いましたが、そのなかには、第2次大戦の補修工事もあるというので、戦争から80年近くなるというのにと驚きました。終戦後、すぐに大聖堂は補修されたのですが、空襲で壊れたがれきなど粗悪な建材を使ったこともあり、1990年代に本格的な保守工事をはじめたそうです。
戦争中、大聖堂は14発の直撃弾を受け、天井には穴があいたところもあったそうです。Wikipedia によると、ケルンは大戦中、262回の爆撃を受け、市内のほとんどの建物は焼失するか崩れていて、当時の写真を見ると、大聖堂の黒々した外観が目立ちます。(下の写真は空襲を受けたケルン市街=米国防省)

大聖堂は1996年に世界文化遺産に登録された文化財ですが、戦争中にこうした歴史的な建造物への配慮がなかったことが驚きです。それどころか、大聖堂のふたつの塔は、爆撃機がケルンに近づく絶好の目印になったといわれますから、大聖堂が破壊を免れたのは、目印を残すためだったかもしれません。私たちが訪れたシュトゥットガルト、ミュンヘン、フランクフルトも町全体が破壊されるような空爆を受けていて、それぞれの文化財も爆撃を受けたといいます。戦略爆撃の象徴とされる1945年2月のドレスデン爆撃でも、文化財への考慮はなかったようです。
そう考えると、原爆の投下予定地の候補に入っていた京都がその文化的な価値から目標からはずされたというのも、絶対的なものではなく、ほかに適当な場所があったという程度のことかもしれません。戦争というものはいつの時代も、文化財も人の生命も相対化されていく。そんなことを考えながら大聖堂を見入っていました。ケルンからフランクフルトへの復路は、ライン川沿いではなく高速道路を使ったので、アウトバーンをたっぷり走りました。
◆国際都市フランクフルト
フランクフルトには2泊しました。それだけの雑ぱくな印象ですが、外国人が多いと感じました。日本人の私から見ると、いわゆる白人はみな同じに見えるので、外国人が多いと感じたのは、肌の色や顔つきから中東系やアフリカ系だと思われた人たちが多いと思ったのです。(下の写真はフランクフルト旧市街のレーマー広場)

ドイツ留学サポートセンターのHPをみたら、「国際企業が多いフランクフルトは、人口に占める外国人の割合も30%と国内でも最も外国人比率が高い」と書かれていました。国際企業で働くビジネスマンも多いのでしょうが、欧州は、中東やアフリカからの移民や難民の受け皿になっていますから、フランクフルトのように国際ビジネスや観光の拠点で活気のある都市には、その底辺を支える労働者としての外国人も多くなっているのだと思います。
たまたま、フランクフルト在住が20年になるという日本人と話をすることができました。外国人労働者について尋ねたら、その人が働いたことのある銀行の食堂では、アジア、中東、アフリカのさまざまな国からの労働者が働いていたとのことでした。「人手不足だから、事務所のバックヤードなどには、外国人労働者が入らないと経営が成り立たないのではないか」と話をしていました。
帰国後に、近刊の『人口亡国 移民で生まれ変わるニッポン』(朝日新書)の著者で、日本国際交流センター理事の毛受敏浩さんの話を聞く研究会がありました。毛受さんは「日本には年に2回、物流と外食が危機を迎える日があります」といって、参加者が何のことだろうかと首をひねっていたら、「それは日本語能力試験の実施日です」と種明かしをしました。調べてみると、コロナ前の受験者数は、年間100万人を超えていました。物流や外食の現場では、試験日は、代替の人もいないお手上げの日になっているのでしょう。

「日本の国民も政治家も、外国人労働者がエッセンシャルワーカーになっている現実を知る必要があります」
この毛受さんの言葉がフランクフルトの日本人が語っていたことと同じだったことに驚きました。ドイツは移民や難民受け入れの先進国ですが、日本も追い付いていかなければならないのは確実です。そこで、問題は、いい方向で日本が「生まれ変わる」ことができるのか、ということだと思います。
毛受さんによると、ドイツでは、ドイツ語教育を中心に移民の教育に力を入れていて、約1000億円かけているのに、日本の同じような予算はその100分の1程度で、日本語教育は地域のボランティアに頼っているのが現実だと語っていました。
私がフランクフルト在住の日本人にもうひとつ質問したのは、外国からの移民や難民がふえたことで治安が悪化したことはないのか、ということです。彼ははっきりと「ない」と、答えていました。フランクフルトのホテルでフロントにいる若い女性にも、「これから夜の食事に行くのだけれど、歩いていって大丈夫か」と尋ねたら、「まったく大丈夫」とニコニコしながら答えていました。
統計を調べたわけではないので、確証はありませんが、在住者の実感としては、治安が悪化して犯罪がふえている、ということはないのでしょう。毛受さんの話を聞いて、ドイツ政府が移民の教育水準を上げることで、治安を悪化させず、社会の生産性も上げようと努力していることを知りましたが、それが効果を上げているのかもしれないと思いました。移民者への日本語教育ですら、予算をかけていない日本の将来は大丈夫だろうか、と心配になります。
ケルン往復の小旅行を終えた翌日、私たちはフランクフルト空港を発ち、無事帰国しました。ドイツでの宿泊7日、機中泊やら時差やらを合わせると10日間のドイツ・ウーラント紀行でした。紀行記の最後は、ウーラントの「旅へ」という詩で、締めることにします。エマ夫人の『伝記』によると、1854年の年の終わり、結婚で米国に旅立つ友人の娘にこの詩を別れの挨拶として作詞したとあります。
旅へ
真夜中、道なき広大な海の上で、
船の灯りがすべて消えたままだったとき、
たとえ空のどこにも星が輝いていなくても、
甲板には小さなランプがまだ灯っていて、
その芯は嵐の風から守られ、
そして、操舵手の針を明るく保ち、
彼が間違わずに進む針路を照らしている。
そう、灯りを守れば、
光は、私たちの胸の中で今も燃えながら、あらゆる暗闇のなか、私たちを導くだろう。
Auf die Reise
Um Mitternacht auf pfadlos weitem Meer,
Wann alle Lichter längst im Schiff erloschen,
Wann auch am Himmel nirgends glänzt ein Stern,
Dann glüht ein Lämpchen noch auf dem Verdeck,
Ein Docht, vor Windesungestüm verwahrt,
Und hält dem Steuermann die Nadel hell,
Die ihm untrüglich seine Richtung weist.
Ja, wenn wir's hüten, führt durch jedes Dunkel
Ein Licht uns, stille brennend in der Brust.
ウーラントの「渡し」は、私たちの人生のなかで、これからも小さなランプの灯りを灯し続けると思います。
◆予期せぬ旅のおみやげ
帰国後、しばらくして釜澤さんがシュトゥットガルトのローカル紙「シュトゥットガルト新聞」とローカルメディア「シュトゥットガルトニューズ」に、私たちの記事が出ているのを発見しました。シュトゥットガルト郊外のホーヘンで「渡し」の現場を案内してくれたツヴィンツさんが私たちの話を提供したのでしょう。詩の舞台になったホーヘンまでわざわざ訪ねてくる日本人がいる、というのは地元では話題性があったということでしょう。わたしたちにとっては予期せぬ旅のおみやげになりました。(下の写真は、シュトゥットガルトニューズのネット版に掲載された記事の一部)

(冒頭の写真はケルン大聖堂を超広角レンズで撮ったもの)
この記事のコメント
コメントする
未分類の関連記事
| 前の記事へ | 次の記事へ |




7回にわたるドイツ紀行有難うございました。卒寿を越して身体が不自由になったいま楽しませていただきました。