マイセンのメルヘンの世界を堪能 泉屋博古館東京の特別展

東京・六本木の泉屋博古館東京で、「巨匠ハインツ・ヴェルナーの描いた物語(メルヘン)-現代マイセンの磁器芸術」と題した当別展を鑑賞、彩り豊かな食器の芸術を楽しんできました。会期は11月3日まで。
◆マイセンの原点は柿右衛門
マイセンといえば、「柿右衛門」の影響が知られています。会場の最初のコーナーは、17世紀後半から18世紀にかけての肥前・有田の皿や人形、碗椀の展示に続いて、18世紀中葉から20世紀後半にかけてのマイセンの皿や鉢、カップ&ソーサー、ティーセットなどが並べられています。順にみていくと、有田の柿右衛門様式がマイセンに伝えられ、発展していったことが自然とわかります。初期のマイセンは、柿右衛門の「影響」というよりは、「模倣」だと思いました。(写真上は《色絵龍虎図輪花皿》肥前・有田窯 江戸時代中期 愛知県陶磁美術館蔵。写真下は《梅樹竹虎大皿》マイセン 18世紀 愛知県陶磁美術館蔵)


この企画展の『図録』などを読むと、1610年代に肥前・有田で最初の磁器が誕生、それが1659年以降、長崎港からオランダ・東インド会社を通じてヨーロッパに伝えられ、欧州の王侯貴族を魅了するようになりました。なかでも、ポーランド王からザクセン選帝侯となったフリードリヒ・アウグスト1世(アウグスト強王、1670~1733)は、柿右衛門などの東洋陶磁器の収集に飽き足らず、「白い金」と称えられた有田の白磁を作るため、首都ドレスデンに錬金術師のベトガー(1682~1719)を呼び寄せました。
ベトガーが硬質磁器の焼成に成功すると、アウグスト強王は1710年、マイセンの出発点となる王立磁器製作所をドレスデン近郊のマイセンにあるアルブレヒト城内に設置しました。1720年代には、化学者だったヘロルト(1696~1775)が上絵付の顔料を開発、マイセンに色絵磁器が誕生しました。世界的な名窯、マイセンの誕生物語です。
柿右衛門と同じようなものを作れ、というのがアウグスト強王の命令だったのですから、マイセンが柿右衛門の模倣となるのは当然だったのです。それがいつのまにか世界的なブランドとなったわけで、柿右衛門様式の本家である日本としては少し悔しい気もします。今回の企画展の内覧会で、ヴェルナーを中心とするマイセンの磁器を出展した勝川達哉さん(アンティーク・アーカイヴ・オーナー)のお話を伺う機会がありました。勝川さんは「マイセンが有田よりも発展したのは、なんといってもザクセン王というパトロンの存在が大きかった。それに、マイセンの高級食器を買える王侯貴族などヨーロッパの富裕層の存在もありました。残念ながら、日本にはそれだけのパトロンも購買層も十分ではなかったのでしょう」と語っていました。肥前佐賀藩の大名(鍋島家)では、ザクセン王に太刀打ちができなかったのでしょう。(写真は、《アラビアンナイト》を横にした勝川達哉さん=泉屋博古館東京で、筆者写す)

ザクセンの都ドレスデンといえば、第2次大戦末期の1945年2月、連合国の激しい空爆を受け、市街地のほとんどが破壊された都市として知られています。前線から離れた都市への攻撃で、国民の戦意を挫く「戦略爆撃」の典型といわれています。ドレスデン爆撃の象徴が爆撃で破壊された聖母教会で、調べてみると、アウグスト強王が建てたものでした。社会主義の東ドイツにあったせいか、廃墟のまま長く放置され、再建されたのはドイツ統一後の21世紀になってからです。
私は2018年に東欧・ドイツを旅行した際、この教会を見ながら、ドレスデンへの「戦略爆撃」について考えを巡らせましたが、マイセンまでは足を延ばしませんでした。高嶺の花を眺めても仕方ない、と思ったのですが、今回の企画展で、マイセンのいろいろな歴史を学び、マイセンを見ておくべきだったと後悔しました。
◆ヴェルナーの名シリーズの登場
マイセンには、《ブルーオニオン》、《インドの花》、《猿の楽団》など、長く愛されてきたシリーズがあります。1960年代になって、《アラビアンナイト》、《サマーナイト》、《ブルーオーキッド》などのシリーズを手掛けたのがマイセンの装飾デザイナー、ハインツ・ヴェルナー(1928~2019)です。(下は、マイセンのHPに掲載されているハインツ・ヴェルナーの写真)

ヴェルナーは1943年、15歳のときに、マイセン養成学校に入り、絵付けなどを学びます。この学校は、ドレスデン芸術アカデミーの分校として1764年にマイセン磁器製作所内に設立されました。絵の才能を見込まれ、1950年代には絵付師として認められます。マイセンは、ザクセン州ライプツィヒで、開かれる国際見本市「ライプツィヒメッセ」に新作を発表し、それをもとに製品化を進めています。その見本市でヴェルナーがデザイナーとしてデビューしたのは1958年でした。
ライプツィヒメッセは、1190年から続く世界最古の見本市で、東ドイツ時代のマイセンにとっては、西側諸国を含む国際ビジネスの窓口になっていました。ここでの評価を得るとともに、欧米の消費動向をつかんでいたのです。マイセンが伝統的なデザインだけでなく、ヴェルナーのようなアーティストを育て、新しいデザインの製品を作るようになったのは、新作に期待するこの見本市があったからでしょう。
そのヴェルナーの名シリーズの誕生ともいえる作品が、1964年頃から制作され《ミュンヒハウゼン》です。実在したプロイセンの軍人、ミュンヒハウゼン男爵(1720~1797)が誇張や創作を交えて話した物語を作家のゴットフリート・アウグスト・ビュルガー(1747~1794)らが潤色したもので、ビュルガー版が世界的に広まりました。日本では「ほら吹き男爵」の名前で知られています。その物語をヴェルナーはモチーフにしたのです。(写真は《ミュンヒハウゼン》コーヒーサービス マイセン 1964年頃~ 個人蔵 装飾:ハインツ・ヴェルナー、器形:エアハルト・グローサー、アレクサンダー・シュトルク、ルートヴィッヒ・ツェブナーの共作)

泉屋博古館東京の森下愛子主任は、展示されている《ミュンヒハウゼン》の黄色のコーヒーサービスについて、「この色を出すのが難しく、歩留まりも悪かったので、今では作るのは困難で、非常に貴重なもの」と解説していました。眺めていると、模様として描かれた男爵の紺色と黄色の素地が補色の関係になっていて、鮮やかな印象を与えていました。
『図録』によると、ヴェルナーは《ミュンヒハウゼン》をきっかけに、1970年代後半にかけて、物語からインスピレーションを得た《サマーナイト》や《アラビアンナイト》などを発表、今ではヴェルナーの代表作になっています。(写真上は《サマーナイト》ティーサービス マイセン 1974年頃~ 個人蔵 装飾:ハインツヴェルナー、器形:ルードヴィッヒ・ツェブナー。写真下は《アラビアンナイト》コーヒーサービス マイセン 1974年頃~ 個人蔵 装飾:ハインツ・ヴェルナー、器形:ルードヴィッヒ・ツェブナー)


《サマーナイト》は、シェークスピアの『真夏の夜の夢』、《アラビアンナイト》は、『千夜一夜物語』をモチーフにしたシリーズで、絵を見ているだけで、楽しくなります。こうした食器で食事をすれば、さぞ会話もはずむだろうと思います。とはいえ、マイセンが新たに制作するのは難しいこともあるのでしょう、日本ではフルセットで1000万円前後の値段で売られているようです。これでは、「高級食器」を通り越して「高額美術品」ですから、はたして実用に供している人たちがどれほどいるのだろうか、という気もしてきます。
◆マイセンの名品を育てた東ドイツ
出品者の勝川さんは、ヴェルナーの名シリーズは、「東ドイツ時代でなければ、生まれなかっただろう」と言います。品質を保つために歩留まりが悪く、ヴェルナーの筆のタッチまで似せる熟練の職人がひとつひとつ手で描いていく作業も効率が悪く、安価な製品が幅を利かせる市場経済の荒波に揉まれれば、名品を作り続けるのは難しかっただろう、というのです。泉屋博古館東京の野地耕一郎館長も「現代マイセンは、東西ドイツの分断で培われ、大切にされてきた」と話していました。
『図録』によると、1960年に創立250年を迎えたマイセンには、ヴェルナーを含むアーティストの集団「芸術の発展を目指すグループ」が結成され、1967年には、アウグスト強王が狩猟に使ったモーリッツブルク城に彼らのためのアトリエがつくられました。このアトリエを象徴するのが《狩り》シリーズです。このグループには、彫塑家や造形師、絵付師らが参加していて、彼らがアイデアを出し合い、協力するなかで、独創的なマイセンが生まれました。「ひとりはみんなのため、みんなはひとりのため、という三銃士の合言葉を彼らも大事にしていました」と、森下さんは解説しています。(写真は《狩り》大燭台 マイセン 1973年頃~ 個人蔵 装飾:ハインツ・ヴェルナー、ルディ・シュトレ、器形:ルードヴィッヒ・ツェブナー)

協力の精神は、職人とアーティストとの間に根付いていて、お互いの信頼関係が品質の高い製品を生む出したようです。社会主義の東ドイツ時代は、職人とアーティストの賃金の格差も少なく、自分たちに与えられた仕事を果たすことで、満足を得られていたのだろうと想像します。
◆柳宗悦の「ギルド社会主義」
社会主義という環境がマイセンの芸術性を高めた、というのは歴史の皮肉のような思いがしますが、考えてみれば、音楽、バレエ、スポーツなどの分野では、資本主義に勝る音楽家、舞踏家、アスリートをたくさん輩出していましたから、不思議ではないのでしょう。こうした分野には、パトロンが必要で、それが王侯貴族から社会主義国家に代わったということなのでしょう。
そこで思い出したのが「民芸運動」を主導した柳宗悦(1889~1961)です。柳は、無名の職人が美を意識せず、黙々と作ったものに作為でない美があるとして、職人が無意識に作り出す美を讃える一方で、美の方向性を示す工芸作家の美もまた必要だと言いました。
柳の理論では、工芸作家は僧侶で、工人と呼ぶ職人は平信徒であり、この両者の協力で「美の王国」を作るには、僧侶と信徒を結ぶ教会のような組織が必要で、それが「協団」だと説明しました。そして「協団」のモデルを中世ヨーロッパのギルドに求め、農業でも、工業でも、商業でも必要なのは「ギルド社会主義」だと主張しました(柳宗悦が1927年に発表した「来るべき工芸」など)。
柳は、職人のつくる日用品に美を見出し、沖縄の紅型を例外として、富裕層が使う高級品を「民芸」から排除しましたから、マイセンに関心は向けなかったでしょうが、東ドイツ時代のマイセンの工場を見れば、柳が理想とした「協団」の姿を思い浮かべたかもしれません。
◆ドラゴンは空を翔ける
『図録』によると、ヴェルナーは1993年にマイセンを定年退職しましたが、1994年には《ドラゴンメロディ》を発表するなど、マイセンでの仕事は続け、教え子たちとの共作にも励みました。(写真は《ドラゴンメロディ》コーヒーサービス マイセン 1994年 個人蔵 装飾:ハインツ・ヴェルナー、器形:ルートヴィッヒ・ツェブナー)、

1990年代というのは、ドイツ統一の時代ですから、国家の許可はなくても、どこにでも行ける自由をマイセンのアーティストたちも味わったと思います。そんな歴史を思いながら、さまざまな楽器を奏でる妖精たちと戯れるドラゴンの姿を見ると、社会主義の束縛から解き放された人々の喜びを感じます。
ヴェルナーが亡くなった2019年、マイセンは「将来の存続を確保するための方策」と題する経営方針を発表しました。高級陶磁器の市場が縮小するなかで、不採算店の閉鎖やオンライン販売の拡大など「戦略的調整」をするために、約3分の1の人員削減に踏み切る、という発表でした。
勝川さんは「熟練の職人たちがマイセンを去ったことで、アラビアンナイトやサマーナイトのような作品ができなくなるのではないかと心配しています」と語っていました。
行列のできる料理店があちこちにあるのは、食事を楽しむ文化が広がっていることでもあるのでしょう。食事を楽しむ文化は食器を楽しむ文化でもありますから、この展覧会は時宜にかなうものだと思います。
マイセンを堪能し我が家に帰って食器棚を見たら、マイセンの《ブルーオニオン》もどきの日本製の食器がありました。妻に聞くと、割れても惜しくない程度の値段だったそうです。有田からマイセンに渡り、再び日本に戻った、などと磁器の歴史を想いながら、この皿で食事を楽しむことにしました。
「巨匠ハインツ・ヴェルナーも描いた物語(メルヘン)―現代マイセンの磁器芸術」は、泉屋博古館東京での特別展を終えたあと、郡山市立美術館(2025年11月22日~2026年1月18日)、愛知県陶磁美術館(2025年春~)、細見美術館(2026年11月21日~2027年1月21日)を巡回する予定です。
| 前の記事へ | 次の記事へ |
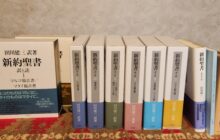

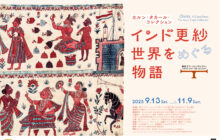

コメントする