『シベリア日記』の積み残し

船山廣治『ハバロフスクにおける榎本武揚』から転載した、プリユスニンの商館
・シベリア日記 ・・・ 積み残し
・シベリア日記を振り返る
榎本のシベリア日記の頁を改めてめくり直してみると、榎本は行った先々で商工業界を代表する人物と会い、ビジネスの話をし、あちこちの金山を見学して金山に関する諸制度を尋ね、各地の行政制度、囚人の輸送の様子や各地での囚人の処遇、現地の写真の収集、特に地域ごとの兵力の動員能力を把握しようとしました。
シベリアならではの馬車、タランタスで移動中、馬車を警察官などが先導していることや、現地司令官が同乗していることに、道にいる農民や街の人たちは気づくと、脱帽し榎本たちにお辞儀をしました。清国人たちは珍しそうにその様子を立ったまま眺めていました。榎本は、人々が私達にお辞儀をする姿を見て西洋人は卑屈な態度と言うだろうし、漢学者が見れば礼儀正しい態度と言うだろうと書きました。榎本の見解を知りたいところですが、その続きは書かれていません。
『シベリア旅行費用計算書』にも計上されていますが、ペテルブルクの公使館を出るところから、帰国するまでの間、自身のために働いた人々に必ず、日本で言えば「心付け」、「西洋」で言えばチップを渡しています。榎本が江戸時代の人だからなのか、国際人だからなのか、自身の社会的ステータスとして当然の行為としているのかは、日記からは判明しません。
榎本が渡す心付けの相場は、一人、2ルーブルという場面が度々登場します。計算書では1円=1r67k、1.67ルーブルで計算されています。rはルーブル、kはコペイカ(カペイカ)で、1r=100kです。この換算率からすると、榎本は日本円で1.2円を基準に渡していたことになりますが、当時のロシアの労働賃金、物価からして、渡されたロシア人の働き手がどう受け止めたのかは専門家に尋ねなければ分かりませんが、極東に近づくに連れ、2ルーブルを受け取って驚く人も登場するので、そうケチな心付けではなかったようです。榎本の肩書からしたら、ケチな金額では国の体面を傷つけますので、相応の金額なのでしょう。(現代価値では感覚的におおよそ5~6千円?)
心付けやチップは、社会的慣習、給与の仕組みだったと言ってしまえばそれまででですが、それが習慣だとしても、自分のために働いてくれている人々に少しながらも心付けを渡し、自身の感謝の気持ちを伝えようとしていた榎本の行為でした。
日記には、タタール人や国境周辺のモンゴル系の人々、フン族、ロシアの農民、清国人、ユダヤ人が登場します。榎本はタタール人やモンゴル系の人々、いわゆるモンゴロイド、黄色人種にはに親近感を感じたようです。また、ロシア人の農民やコサックの生活の貧しさにも関心を向けていました。
榎本のみんなの生活を豊かにしたいという心底が伺われます。もう一つ心底が丸見えだったのが美人に関する記述です。榎本の美人の基準は分かりませんが、「美人」という言葉がときどき登場します。「美人」という言葉は、女性だけでなく男性にも向けられるので、日本人を基準にした美術的観点だったようです。
お茶をロシアへ輸出することに大きな関心がありました。静岡藩へ移住した徳川幕臣たちは、例えば牧之原台地を開墾して、お茶の栽培を始めました。お茶の輸出機会を増やそうとすることは、旧徳川幕臣の生活のため、榎本にとって重要な仕事でした。
清国はお茶、絹の最大輸出国ですから、清国は日本からのお茶、絹の輸出先にはなりません。お茶を大量に輸入しているロシアへ日本からの輸出が、榎本の狙いでした。これは恐露病患者とは随分、立ち位置が違います。相手を恐れて逃げ惑うのか、相手を利用するのか。これは武道を学んだものなら分かることです。とは言え、お茶の貿易の話を隠れ蓑にして兵力の把握、動員時の移動距離などを知ろうとしていたようにも思えます。
当時、大陸へ軍を侵攻させ領地を拡大するのか、産業を興し大陸への輸出を拡大するのか、政府主流派(薩長閥)と非主流派(旧幕臣、旧佐幕派)の代表、榎本ととの間で列強国観、国家政策観は大きく違いました。この大きな違いが、帰国後の榎本を苦しめることがありました。
榎本が出した結論に加えるべきもう一つの項目が、諜報活動です。ペテルブルクで新聞の噂記事にあったと榎本本人が言う、中央アジアのブハラへ3万の精鋭部隊集結について、現地では状況が違っていることに、榎本は強い関心を持ちました。榎本の頭の中の知識ルールが書き換えられたかもしれません。
日露戦争の大本営陸軍参謀部による諜報活動の情報源の一つに、「ロシア政府が出す公報」があります。陸軍参謀部の誉田甚八*は日露戦争を次のように回想しました。
『政府は、毎月『露軍配置書』を公刊して在極東戦地に在る部隊を記載していたのみならず、新たに編制動員する部隊はこれを公報で公示し、その編制までもが新聞に掲載されていたのである。大本営陸軍参謀部はこれにより戦地に使用されているロシア軍部隊を精確に把握することができたため、諜報業務が容易となった。』
『若し此の公報なかりせば、露軍の如き種々なる編制ある部隊を如何にして審にすることを得んや』
*長南正義『新資料による 日露戦争陸戦史』並木書房、2015、p.671 誉田甚八(1870‐1909) 金沢出身、陸軍大学卒。
しかし、榎本のチュメニでの体験からするとこの回想は事実とは思えません。むしろ、榎本の経験が引き継がれ、日本の諜報部門はロシア政府の公報を把握しながらも、現場でのチェックを怠らなかったと考えられます。
さらに、榎本が現地で熱心に現地の写真を収集していたことは、当時、情報収集と報告の最新スタイルでした。現代では衛星写真です。榎本がわざわざユーラシア大陸を横断する目的に、極東のグレート・ゲーム、ロシアの南侵を監視するために、今後の諜報活動をどうするかを模索することも、もう一つ重要な仕事としてあったのでした。
榎本の諜報活動は科学技術の手法と同じでした。兆候を把握して真実を悟れ、です。片っ端から調べることを科学技術では総当り法と言います。総当りをしてようやく実態、全体像が分かってきたというのでは、科学技術としては失格です。特徴的な事実、実験を把握し、その部分集合から全体集合を推定することが科学技術の典型的思考方法です。
そして、可観測可制御性の原理があります。非常に簡単に説明しますと、計測できることのみ制御可能なのです。諜報活動は仮想敵国の軍事行動、我が国の国益を毀損する行動を計測する手段です。榎本は、極東でロシアが南侵する兆しをいち早く把握する計測手段である観測網、諜報活動網の準備をしていたと考えられます。
・物価表や兵士の数
榎本は行った先々で物価を聞いては記録し、街に駐在する正規兵とコサック兵の数を聞き、有事の動員数も聞いて回りました。兵士の数を聞くと時には相手から嫌そうな顔をされましたが、それでも、気を使いながら聞き続けました。
物価表や商取引の統計を聞くことは、一つには日本国民の商機を模索するためでしたが、さらにもう一つ理由がありました。ナポレオン軍が活動する時期から兵の糧食を現地調達することになりました。あくまで現地調達であって現地略奪ではありません。軍が侵攻先の現地住民に費用を支払って、糧食を買い上げます。そこで、物価情報は軍にとっても重要でした。
さらに、兵員数を把握しておくことは、外交上も有事を目の前にしたときにも重要な情報になります。平時、常駐する兵員数と動員能力を知ることは有事を前にして、相手国が投入しうる兵力を想定するために重要な情報です。実際にタシケントの総督は、三万人の精鋭を集合させたとき、2千キロ以上も離れた基地から兵を徒歩で動員したことを榎本はチュメニで確認しています。
極東でロシアが国境を超えて清国側に攻め入るときも同様に、極東から遥か離れた基地から兵が動員されてくることになることが榎本には分かっていました。その最大動員能力を把握しておく必要がありました。
・地理学、博物学
榎本は1878年(明治11年)8月29日、イルクーツク府で各界トップクラスの人々と面会しました。その日、フィールドノート(小型手帳)から日記に採録したという文章は以下の通りでした。
『シベリア火成地のこと
フォン・フンボルト氏はイルクーツクをもって火成の地と言った。・・・』
フォン・フンボルト氏とは、アレクサンダー・フォン・フンボルト(Alexander von Humboldt, 1769-1859、ドイツ)、地球学(地理学)の祖と言われる人です。1840年に文献上、初めて科学者、scientist*という言葉が登場しました。フンボルトは哲学から地球科学を独立させた科学者でした。フンボルトは「地理学の根本概念『コスモス』』という地理学の古典を書き上げ、地球科学を誕生させました。
*鎮目康夫訳、バナール『歴史における科学 Ⅰ』みすず書房、1967
地理学協会は、1821年にパリ地理学協会、1828年にベルリン地理学協会、1831年に英国王立地理学協会、その後続々と設立されていきました。榎本がオランダに留学していた時期(1863-1866)に、世界の海でビジネスをしてきたオランダの海軍から軍人として世界を知るためにフンボルトの学問的業績とドイツ地理学を学んだはずです。
その日の榎本の日記を読み直して見ると、当日は軍や行政の幹部連に会っていて、火成のことがフィールドノートに書き留められていたものだということを合わせ考えると、その日に会った誰かに言われたか、訪問した政府所管の鋳金場で教えてもらったのか、印象的な内容だったので、聞いてすぐ持ち歩いていたフィールドノートに書き留めたのだろうと考えることができます。
また、春之助の写本では、この箇所の本文では「火製の地」と書かれています。当時、手紙では音が同じ漢字を当てることが多かったので、榎本はこの「火製」は「火成」と書くところ、同音で当てたのか、それとも本当に「火製」であり、火山が製造した土地と言いたくて「火製」と書いたのかは、今となっては推測の域を出ることはありません。
榎本が、フンボルトのどの研究からイルクーツクは火成という知識を手に入れたのか興味が湧き、少し調べてみましたが、見当たりません。かの有名な『コスモス』(Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung、宇宙.世界の物理的記述の草案)の中にでもあるのだろうと考えてみましたが、該当しないようです。
2009年(平成21年)3月23日の、東京農業大学総合研究所榎本・横井研究部会で、会員であった故西川治東京大学名誉教授が榎本とフンボルトについて研究発表をされました。ダグラス・ボッティング著、西川治+前田伸人=訳『フンボルト―地球学の祖』(株式会社東洋書林、2008)に収録されている西川氏の「A・フンボルトと日本―幕末から明治にかけてー」という題名の論文を基にした発表でした。
フンボルトがロシアの皇帝に依頼されて、シベリアでいろいろ調査、探検したことをまとめた本、『中央アジア』第二巻を見る限りフンボルトはイルクーツクへは行かなかったと西川氏はみています。それではと『コスモス』の第四巻で火山現象とその地理的分布について詳論している箇所をざっと目を通してみても、ここでも関係した地名は登場しないそうです。
榎本の研究者である加茂儀一と井黒弥太郎がこの箇所を取り上げ、榎本はフンボルトが火成の地と指摘したことに疑問を持っていたのだろう、このまま調査を続ければフンボルトの誤りを解くという偉業をなし得ただろう、さすがに榎本の着眼点は違う、と榎本を評価しました。しかし、西川氏の論文では、加茂儀一と井黒弥太郎の指摘は誤りだったと論じています。
西川氏はバイカル湖及び周辺に火山活動の地形を確認した2003年発表の論文を紹介しています。2001年には東北大学から『Bartoy火山地帯(ロシア・バイカル地方)のアルカリ玄武岩に由来する捕獲岩とメガクリストについての新データ』(原文は英語)という論文が発表されています。玄武岩は火山から噴火した溶岩を特徴づける岩石です。
もし、榎本がペテルブルグでフンボルトのこの知識を手に入れて、ようやくイルクーツクにたどり着いて、火成を示唆するものを観察しようとしていたのなら、その知識を手に入れる可能性がある場所は、帝立ロシア地理学協会です。
ロシアの地理研究、辺境研究が盛んになった1820年代から地理学協会の設立機運が高まり、ロシア地理学協会は1845年8月6日に設立され、1849年から帝立になりました。地理学協会は専門家のみの会ではなく、ロシアを知ろうとする人々に開放的でした。当然ながら、ロシアの地理学は地理学の発祥の地とも言えるベルリン大学を拠点とするドイツ地理学の圧倒的影響下にあり、地理学の父、フンボルトや地理学の礎石を築いたカール・リッター(1779-1859、近代地理学の父と称賛されている)は名誉会員でした。
榎本は、ペテルブルク在任中、帝立ロシア地理学協会の会員になりました。1854年3月、18歳のとき、榎本は箱館奉行、堀織部正利煕(ほりおりべのしょうとしひろ)の小姓として蝦夷そして北蝦夷を巡回しました。北蝦夷とは樺太島のことです。その年、足掛け3年をかけてロシアの動物学者*が樺太島を調査していました。榎本が彼らと遭遇していた可能性もあります。
*この動物学者は『アムール地方の異族人について』という調査結果をドイツ語で発表した。
1855年から1863年にかけた地理学協会の樺太調査の結果によると、北緯48度以南の日本支配の確立を認めていました。樺太の生態系が北日本の延長上にあることと樺太のアイヌたちに日本式生活習慣が相当浸透していること、生活用品のほとんどが日本製であること、日本政府が教育、医療など物質面の向上に援助していることなどが日本支配の根拠でした。こういった樺太に関するロシア側の調査結果も榎本の外交交渉を後押ししたのでしょう。
榎本は帰国後、渡辺洪基(わたなべひろもと)の主導のもと花房(1842‐1917、岡山藩士、ペテルブルグで榎本を補佐)らを加えて1879年4月に英国王立地理学協会をモデルとして「東京地学協会」を創立しました。ロイヤルソサエティをモデルにしたことは、地理学と国家との関係を榎本は幅広く理解していたことを示します。
(ロシア地理学協会については、天野尚樹『極東における帝立ロシア地理学協会:サハリン地理調査を手がかりとし(ロシアの中のアジア/アジアの中のロシア(3))—(トランスボーダーの地政学)』「スラブ・ユーラシア学の構築」研究報告書(17)、2006を参照、引用した)
榎本は日記にバイカル湖でお寺の鐘が鳴るくらいの大きな地震が度々起きるようだと書きました。実際、日本の気象庁作成の平成20年8月に世界で起きたM6.0以上の地震の一覧表(19件)には、同年8月27日にバイカル湖を震央とするM6.2の地震が記載されています。本当はバイカル湖の地質についても榎本はもっと調べたかったことでしょう。
・生物の成長を考える
1862年12月28日の渡欄日記によると、榎本は船中の若い官医と食後、12時まで物理学の話題で話し込みました。その官医は『光素はインポンデラビリア(非常に軽きもの)と名付けおきしものの一つなりしに、近来一究理学*の説にこれまた、』と物理学の話しは続きました。
*究理学または窮理学とは、当時の物理学の呼び名。
1864年にマックスウエルの方程式の発表により光の波動性が明らかにされる以前、ニュートンの光の粒子説がありました。このときの話し相手の官医は25歳、榎本は27歳でした。お互いに最新の物理学の話に花が咲きました。榎本の物理学に関する素養が分かる日記の記事でした。
しかし、榎本の見識は、物理学にとどまらず生物の、しかも成長や形態にまで広がっていました。ミハイロフスカヤ駅(黒河市-璦琿城の手前の駅。現、ミハイロフカ)でチョウザメが榎本の食事に提供されました。すると、科学技術者(工学者、エンジニア)の榎本は、チョウザメの寸法を三尺と判断するのみにとどまらず、背筋を通る三筋の鱗の数を数えます。三筋とは背筋とその左右の筋です。それぞれ一筋あたり35枚だったと同席の人々に語りました。
数える、計るは科学技術者の本能のような行為です。ここで榎本は2つの重要な知見を示しました。1つ目はこのチョウザメは『かならず北海道の石狩や天塩などの川にも存在するだろうと思っていたので、その形をつくづくと眺め、・・・』と日記に書いています。
2点目は、生物の成長についてです。チョウザメの体が成長するに従い、体表を覆う鱗の数が増えるのか、鱗も大きくなっていくのかを昼食のチョウザメを前にした同席の人々と議論しました。議論の最後に榎本は『子どもも大人も手足の骨の数は異なることはない』と発言し、成長につれ鱗が大きくなり、鱗の数は変わらない*と主張しました。ここで議論は終わりました。
*川端真路『魚の成長ととくちょう』http://laboorca.web.fc2.com/04sakanasmall.pdf、平成25年
榎本の知見は驚くべきものです。よく榎本の地質学の知識を称賛する文章に出会いますが、軍のエンジニアであった榎本が地質の知識があることは当然です。しかし、生物の成長には生まれたまま大きくなる生物と脱皮を繰り返さなければ大きくなれない生物に分かれますが、榎本の鱗の数と人体との比較論、この榎本の生物の成長の論考には驚きです。
生物の形と成長に関し、以下のダーシー・トムプソン(1860-1948、英国人)の研究があります。1917年が最初の発表です。
On Growth and Form,by Sir D'Arcy Wentworth Thompson (1860–1948), First written in 1917, revised by Thompson in 1942
戦後、Cybernetics*1の誕生に影響され、故高木純一早稲田大学名誉教授の主導で始まった早稲田大学理工学部の人間理解のためのロボット研究は、ダーシー・トムプソンの論文からも影響を受けました。そして、高木の自動人形の歴史の研究により、日本の自動人形は下半身が動くことに特徴がある*2ことが分かり、故加藤一郎早稲田大学教授の指導で、二足歩行ロボットが研究され、世界最初に研究が完成しました。(1973年、WABOT-1)
*1 Cybernetics副題 動物と機械における通信と制御
Cyberneticsは動物―人間と機械の制御の理論を統一し、その最終目的は、人間が失った機能を機械と組み合わせて取り戻すことにある。Cyberneticsの影響を受けて始まった早稲田大学理工学部のロボット研究の最終目標もそこにあり、高木は研究が人類、すべての人々の平和と幸福を実現することを目指した。加藤は高木の一番弟子であったので、高木の理想に従い、研究を指導していた。
*2 高木の研究成果から加藤は「茶運(くみ)人形」を復元し、自動人形の仕組みを確認した。
榎本が生物の形と成長に関して本格的な研究を続ければ、ダーシートムプソンに先駆けて生物の成長と形について、研究成果を出したのではないかと、この日記の箇所に興奮を覚えます。
・写真館が諜報活動の拠点になる
・絵が少ない
榎本の初の海外渡航であるオランダへの航海中に書かれた渡欄日記を見ると、例えば赤松大三郎の日記の絵と比べて、見ている方を唸らせるほどには絵が上手いとは言えません。箱館の戦友となった陸軍砲兵大尉ブリュネの絵とはさらに比べ物になりません。ブリュネは砲兵隊なので、敵地へ潜入し、着弾点の情報をさっと絵にして戻ってこなければならないので、絵が素早く描け、対象の特徴を捉えて上手に描けることは当然かもしれません。それに比べ、軍艦のエンジンルームにいて蒸気機関を操る榎本には機械の図面は重要でしたが、絵を用いた現地報告が求められなかったためか、日記中に絵は多くありません。
開陽で機関長を努めた小杉雅之進(1843-1909、明治以降は雅三)が箱館戦争を記録した「麦叢録( (ばくそうろく)」*に描かれた絵は上手でした。榎本が機関士だから絵が得意では無いという説明はできません。絵が得意か否かの議論は置いておいても、シベリア日記での絵は少なく、旅行中、訪問地の写真を現地の写真師に度々求めます。榎本の活動状況から、絵を書いている時間は無かったようでした。
*橋本進『咸臨丸還る』中央公論新社、2001に収録されている。
・ハバロフスクの写真館
榎本のハバロフスクでの行動については、榎本のシベリア日記に基づいて、船山廣治『ハバロフスクにおける榎本武揚』一般財団法人北海道北方博物館交流協会会誌(26)、2014で論ぜられ、最後尾に『榎本の、ハバロフスクにおける足跡については不明確な処がありさらに調査のうえ正確を期したい。』と述べています。
2019年10月11日(金)、榎本家第五代目の榎本隆一郎氏から、桐生タイムスのコピーが私に送られてきました。桐生タイムスの晦魄環照(かいはくかんしょう)という連載記事に『竹内テルのロシアの時間』という記事が3回連載されました。この記事に竹内テルと黒龍会の内田良平*1との交流が取り上げられていました。黒龍会関連記事*2なので隆一郎氏がコピーを送ってくれた所以です。
*1黒龍会と内田良平については、別途、紹介します。
*2関連資料 http://kiryutimes.co.jp/regional-news/12914/
桐生タイムスによると、『黒田は、越後長岡藩の軍事総督河井継之助を救えなかった悔恨を繰り返すまいと、榎本を新政府に迎える道を慎重に描きつつ、・・・』、『テルは71年、桐生の近在久方村の和田家の長女として生まれた。兄一人、弟二人。その兄が河井継之助の遺児正秀である。父の和田勇七がすべて承知の上、彼を長男に迎え入れたのだ。』
正秀は黒田の援助のもと1885年(明治18年)に米国へ留学しました。黒田は正秀を留学に出した翌年の86年(明治19年)、榎本と逆コースでシベリアを横断し、さらに外遊を続け、世界一周視察旅行をしました。正秀は、1888年に父勇七の訃報を受け、帰国し、妹テルを愛知県出身の竹内一次に嫁がし、母を除籍し他家へ移すなど行い、一家をたたんで東京へ行き、刀剣鑑定家になりました。この出来事は地元では正秀の奇行と揶揄されたそうです。その後、テル夫妻の極東(ハバロフスク)での事業が軌道に乗ると、兄弟たちの活動地域は極東に移動しました。
竹内テルの兄(越後長岡藩軍総督の河合継之助の遺児で、和田家の養子となった)は黒田清隆と関わりがありました。黒田と榎本とは関係が深いものがありました。黒田は榎本が1878年(明治11年)にシベリアを探査して帰国した後、1886年(明治19年)に自身が、ウラジヴォストークから遥か北方のアムール川河口付近のニコライエフスクから汽船に乗り、世界一周視察旅行を始めました。アムール川のハバロフスクとニコライエフスク間を榎本が旅行しなかった分、黒田が代わりに旅行しました。
榎本が当時十数年後にロシアのパワーは極東に及ぶと報告してから8年後に黒田は、シベリアの様子を確認するがごとく、役割分担された7名が随行して出かけました。これは、榎本のパイロット的調査に続く、黒田の本格的な調査旅行でした。黒田の旅行の大半は、シベリアを中心としたロシアの視察に日数が費やされていました。
1895年(明治28年)の三国干渉後、テルは95年に夫、一次と共にウラジヴォストークに渡り、夫婦*で雑貨店を始めます。翌96年、ウスリー鉄道開通によりハバロフスクへ移り写真館を開業しました。現地の様子を示す写真は重要な情報でした。もし、ハバロフスクに写真館を置いて諜報活動の拠点にすると榎本が考えていたならば、そのアイデアが、黒田を通して竹内テルらに伝播していたはずです。その後、この写真館は日露戦争に備えて日本陸軍の諜報活動の拠点としての役割を果たしました。
その写真館に盛んに出入りした一人が内田良平でした。内田は黒龍会を創立し、主幹でした。内田は日露戦争開戦に非常に強い関心と野心をもっていました。前述の論文、船山廣治『ハバロフスクにおける榎本武揚』2013でハバロフスクでの榎本の行動で解明されきっていない部分があるという指摘がありましたが、その部分とは榎本が重視するハバロフスクでの諜報活動の下地を検討していた部分と考えられます。黒田の旅行には、榎本の意見を実況見分する目的もあったと考えられます。
*竹内夫妻は写真館を開業後、旧名ホテル・ルーシーを建設した。建設地は、『榎本が立ち寄ったプリュースニン*邸とは5.6分の距離。』だった。現在、この建物の状況は、記事に『竹内一次とテル夫妻が建設した旧ホテル・ルーシーはこの通りの角地に面している。完成から100年以上を経た現在でも、真新しい姿で活用されていた。』と紹介されている。
アンドレイ・プリュースニン(1827- 1880) ハバロフスクの豪商。毛皮の取引で財をなし、慈善事業にも尽くした。松花江を利用した交易に力を入れていた。
榎本の日記に戻ります。9月17日、ブラゴヴェーシチェンスク(ブラゴヴェシチェンスク)でユダヤ人写真師に現地の写真を撮ってウラジヴォストークの日本の公館へ送るよう依頼したところ、3枚で25ルーブルを要求されました。この殿様値段に驚いた榎本は絶句しました。同行していたロシア官憲らが高すぎると写真師を咎(とが)めたので、一枚5ルーブルになりました。感覚的に1ルーブルが5千円と考えると、それでも一枚、2万5千円です。
その後、榎本は値切りすぎたのではないかと、ユダヤ人写真師を少しばかりか気の毒に思ったものの、『ユダヤ人はことに商取引で損失を甘受するような民族ではないのでそのままに過ごしておいた。』のでした。榎本のユダヤ人観の一面を示す記録でした。
・帰国後のチーム員たち
帰国後、榎本のチーム員の市川は東京外国語学校でロシア語の教師に、寺見はウラジヴォストークの事務官に、大岡金太郎は陸軍で写真技術者になりました。明治19年6月23日に黒田清隆は東京から作業分担した七名のチームで出帆し、200日間かかけて世界旅行をしました。市川は通訳として黒田に随行し、再びシベリアを目指しました。
また、ウラジヴォストークで榎本たちを出迎えた鈴木大亮は北海道庁理事となって黒田に随行しました、そして、黒田たちをウラジヴォストークで出迎えたのは寺見事務官でした。貿易事務官*の瀬脇寿人は、残念なことに、榎本が帰国した翌月、治療のために帰国する船中で亡くなりました。西周たちは、幕末、瀬脇の私塾で外国語を学びました。瀬脇の後任は、榎本の箱館戦争の戦友、松平太郎でしたが、薩長の政府で働くことに嫌気がさして退職していまい、さらにその後任として寺見が三代目の貿易事務官になっていました。
黒田一行のウラジヴォストークでの輸入の調査によると1885年(明治18年)のウラジヴォストークでの輸入額の順位は、1位ドイツ、2位ロシア(国内から極東へ)、3位日本、4位以下清国、英国、米国でした。日本からの輸入品は順に、小麦粉、小麦、白米、食塩、醤油、・・・とあり、残念ながら日本茶は登場しません。アムール川を利用して日本茶をロシアに輸出するという榎本の望みはまだ実現していません。
黒田一行は、ハバロフスクに一泊しました。璦琿城(あいぐんじょう)では、チチハルへの新道を作り、チチハル経由で盛京(現、瀋陽)に至る電信線路を建設中でした。ストレテンスク(現、スレテンス)に着くと黒田たちはシベリア名物の馬車、タランタスに分乗しました。
このときの調査旅行の様子を明治20年11月に黒田は『環遊日記』と題した本にして出版しました。黒田の本には多数の地図や挿絵があります。但し、榎本の日記のように意見、感想などは書かれていません。外交上、割愛したのでしょう。
ロシアのパワーがシベリア(極東)に及ぶのは十数年後であるという榎本の予測の半分の年数が経過したちょうど8年後に、黒田は内閣顧問という閑職だったので、ロシア政府によるシベリア開発の進捗状況やロシアの変化を調査するため、世界一周視察旅行に出かけたと考えられます。黒田の旅行は榎本の『シベリア日記』の情報をもとに計画され、情報をアップデートしようとした意図は明白でした。1888年(明治19年)の黒田の世界旅行は、榎本のパイロット的なシベリア調査旅行をフォローアップする本格的な調査旅行でした。
・恐露病患者の代表者は山県有朋
榎本は恐露病患者を安心させるためにユーラシア大陸を横断し、シベリアの現地情報を収集(探偵)し、国民に公表しようとしました。では、恐露病患者はどんな人達だったのでしょうか。榎本の手紙に山縣が榎本のシベリア視察旅行に関心を持っていると書いていることから、榎本が山縣こそが恐露病患者と言いたかったことが分かります。
榎本からもたされたロシア南侵に関する見通しと対応には陸軍は登場しません。対馬-釜山の軍事力増強と戦略拠点化、ウラジヴォストークへのシーレン遮断は海軍の仕事だったからです。明らかに陸軍の仕事といえるものは諜報活動でした。諜報活動は表面化しないことで成功ですから、陸軍を代表する山県には不満だったはずです。もっとロシアへの恐怖を増やし、恐露病患者が陸軍増強を叫ぶようにしたいのに、榎本の結論では、陸軍は日陰もので海軍増強がロシア南下を妨げる答えでした。しかも、榎本は日本からロシアへの輸出を増やすことに強い関心をもっていました。日記では日露戦争どころではありません。山県は榎本の『シベリア日記』が国民に公開されることを嫌っていたと考えられます。(憶測の域を出ませんが)
・アムール、黒龍江、黒竜江
アムール川はロシアと中国の国境なので、ロシア側の名前、アムール川、中国側の名前、黒龍江とそれぞれの国の呼び名があります。
榎本は、アムールの名前の由来を9月15日に書いています。
『黒竜江はシルカ川の下流をなすもので別の川ではない。ただ、シルカ川にアルグン川が流れ落ちるところからアムールという名を負うのである。
カピタンの言では、アムールとはモンゴル語のメンドモールから分かれたもので、「シルカとアルグン二つの流れが出逢ってご機嫌がよい」という意味からとっている、と。これは昔からの言い伝えで、カピタン自身の考えでないことは明らかである。」』 (『現代語訳 榎本武揚 シベリア日記』平凡社ライブラリー)
21世紀研究会編『地名の世界地図』文春新書、2020ではアムールの語源を次のように説明しています。
『アムールは、アジア系の様々な「水」をあらわす言葉 (韓国語のムル、モンゴル語のムレンなど)の語幹からではないかとされており、おそらくその意味は「川」だ。中国名のヘイロンチァン(黒龍江)は、満州語サハリエン「黒い」とウラ「江」が中国語化したもの。この川が流れるモンゴルでも(満州地方の呼称に影響されてか)ハラムレンとよばれ、ハラ「黒」、ムレン「川」で「黒い川」である。』
榎本の日記では「アムール」や「黒龍江」と書き記されました。榎本がどう使い分けたかを日記には書かれていませんし、規則性がはっきりしませんが、ロシア側の話題の記録にはアムール、清国側の話題には黒龍江を用いる傾向が見受けられます。
日記では黒竜江は黒龍江と記されています。レファレンス共同データベース*によれば、「昭和二十九年三月の当用漢字補正案に選ばれた際、「龍」は「竜」に字体整理された。」また、常用漢字体表には竜とされています。そのため黒竜江に表記が変わりました。
*引用元:https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000250758
下図は、黒田清隆『環遊日記』(明治20年)から転載したニコライエフスクでアムール川に係留されている汽船
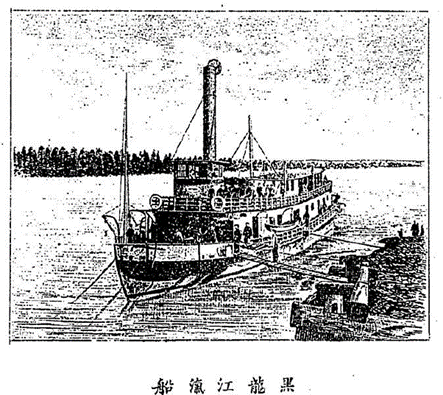
以上。
社会 | 政治 | 文化 | 国際 | 経済 | 歴史の関連記事
| 前の記事へ | 次の記事へ |




コメントする